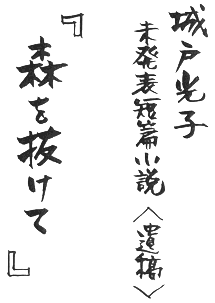
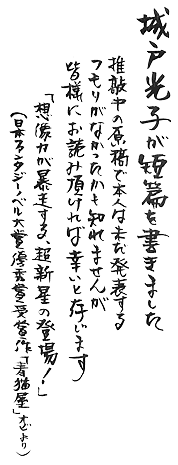
著:城戸光子 紹介・題字:斎木信太朗
ぼくは思わず「待って」と声をかけたのだった。
逢(お)う魔が刻(とき)、というのだろうか、暮れかけた憂鬱な空の下、森が黒くわだかまっていて、その中へ入っていこうとする小さな人影は、見たところ十二かそこらの女の子らしかった。だって、危ないじゃないか、そんな時間にたったひとりで暗い森へ入っていくなんて。だから、ぼくは「待って」と声をかけたのだった。
人影はぴょんと跳び上がってから、こっちを見た。おびえた小動物みたいにせわしなく息をしているのが見てとれた。小さな両手を胸に当て、すこし猫背になって肩を上下させていた。が、眼だけはきらきらと、ぼくの方を窺(うかが)ってた。なんだって? 危ないのは森じゃなく、危ないのはこのぼくなのか? 大きなリュックを背負い無骨な靴を履いた見知らぬ男であるぼくが、一歩でも彼女の方へ踏み出せば、彼女は魂消(たまぎ)る悲鳴を上げ、森に逃げ込むのだろうか? そうか、そうにちがいない。危ないのは森じゃなく、危ないのはこのぼくなのだ。
当時のぼくは、何もわかっちゃない若造だったけれども、体格だけは一人前をはるかに超えた大男で、おまけに無精髭まで生やかしていた。これはすこしでも憂い顔に見られたいという浅薄な考えでもってしていたのだが、まるで逆効果だったことに気づいたのはずっと後年のことである。
ぼくは物柔らかく細い声で、それでもなるたけ遠くへ届くように心がけて、こう言った。どうか、ぼくを怖がらないで。
小さな人影は胸に当てていた両手を解き、ぼくの正面に向き直った。ほんのすこしだが肩をそびやかして毅然とした態度に見えた。ぼくは続けてこう言った。
「ぼくはただ、ちょっとおどろいたので声をかけただけなんだよ。だって、もう間もなく暗くなるこんな時間に、年若い娘さんが森の中へ入ってゆくだなんて。勇気はあると思うけれど、怖くはないの?」
「怖くはねえよ」と彼女は叫んだ。はじめて耳にするその声は、凛々ととんがって、ぼくの胸を突き刺した。見た目ほど彼女は小心者ではないらしい。ぼくは慎重に一歩を踏み出した。女の子もまた、逃げるどころか大きく一歩、距離をつめてきた。そして言い放った。
「ちかみちっ」
「え?」ぼくは聞き返した。
「ちかみちっ」再び言って森を振り返り、指差してみせた先には木(こ)の間(ま)隠れにチラチラと、かすかな光が動いてゆくのが見えたのだった。
ぼくは理解した。近道なのだ。光は自動車のヘッドライトにちがいない。今ぼくらがいるこの道は、ぐるりと森を迂回して、あの道に続いているのだろう。
「「あんた、なに」さらに肩をそびやかし、彼女が訊いた。
「見た目は悪いけど、ぼくは怪しい者でも危険な者でもない。ごらんのとおりの旅行者だよ」背中のリュックを揺すって見せた。それはとても重く感じられた。たいそう歩き疲れていたのだった。
「どうやらね、地図を読み間違えて道に迷ってしまったらしいんだ。だってね、坂をずっとくだっていたはずなのに、いつのまにかのぼっているんだもの、まいったよ。ぼくは見た目よりずっと間抜けな人間なんだ」安心させるつもりで少し笑って見せたのだった。彼女も笑った。それは、ケッケと聞こえた。
「道さえ間違えなければ今頃は○○の町に着いて荷物を下ろし一息ついていただろうに、なんてこったろう」ぼくは溜め息を吐き、あまり期待もせずに訊いたのだった。「この辺りに旅館なんてものはある? もちろんそんなに気の利いたんじゃなくたっていいし、民宿みたいなものでもかまやしないよ。むしろそのほうがありがたいくらいだ。なにしろ貧乏旅行のさいちゅうだからね」
「温泉ある!」と女の子は叫んだ。
「温泉だって?」
「温泉。温泉」と叫びながら左手を大きく上げて指し示したその先は、しだいにせり上がる森の上を飛び越えて、向う側の道のずっと上の方であった。遠く目を凝らせば確かに頼りなく立ちのぼる湯煙らしきものが見えるではないか。そうか、温泉か。ありがたい。急激な寒さを感じて、ぼくはぶるっと震えた。シャツは冷たくなった汗で背中や腋にへばりついていた。季節は秋。先刻までの陽気はどこへやら、こんな山の中では気温の変化がいちじるしいのだ。そうか、温泉か。ありがたい! ぼくはにっこり微笑みかけた。
「ちっこい温泉」彼女は子供らしく首をすくめた。恥じているようであった。
ぼくはことさら陽気に喋った。「ちっこい温泉なら願ったりかなったりさ。きっと親切な夫婦がふたりきりで切り盛りしているような宿なんだろう。部屋も三つか四つしかなくてさ、畳も古ぼけて茶色になってはいるけれどじつに丁寧に掃除が行き届いていてさ、申しわけなさそうに差し出される夕飯のお膳だって豪華というには程遠い。程遠いけれども夫婦の真心が込められているのだ。そうだろう?」
女の子は驚いたように眼を見開き、いちいち大きくうなずいて聞いているのであった。遠くたなびく心細げな湯煙を見上げてぼくは言った。「なんて運がいいんだろう。今夜はあすこに泊めてもらうことにしよう」
女の子はもう一度、ちかみち、と言った。それは幾分か物問いた気な、つまりはあんたもあたしといっしょにこの森を抜ける気はあるのかと問うような、やや尻上がりの言いようなのであった。
今ぼくらが立っている道は、森をぐるりと迂回して、それをさらに登ったあたりにかの宿はあるのだ。馬鹿正直にこの道をたどってゆけばおそらく何倍もの距離を歩くはめになり時間もたっぷりかかるに違いない。ぼくはとても歩き疲れていたから、近道はありがたい申し出であった。ただし、すこしだけ問題があった。もちろんぼくは危険な男でもなければ悪い人間でもないつもりだけれど、ロマンティックな雰囲気に呑まれやすい傾向にあるとの自覚があった。こんな時間にこんな森の中を――たとえ短い時間であるにせよ――若い女の子と――ちょっと若すぎるにしても――ふたりきりで歩いてゆくなんて……。ぼくはふと思いつき、腰にぶら下げておいた懐中電灯を差し出した。「これ、君が持っておいでよ。道案内をするのは君なのだから足下を照らすもよし、もしも何か剣呑(けんのん)な奴が君に悪さをしようとしたらこれでぶちのめすこともできる。もし、もしも万が一それがぼくであったとしても遠慮はいらないからね」
すべてを言い終わるより早く、女の子は走り寄って、ぼくの手から懐中電灯をかっさらい、空いたほうの手でぼくの右手を掴んで引いた! ぼくはつんのめり、情けない体勢を立て直すひまもなく彼女に引かれて行った。彼女の手は小さく力強くカサついて荒れていた。息を弾ませながらぼくは訊いた。
「あなたはいったい――」いったい――何を訊こうとしたのか我ながら判然とはしなかったけれど、なにしろ彼女はこう答えた。
「百姓の女は忙しい。んで、急がねばよ」
間近(まぢか)で見る彼女の顔も髪の毛も、その手と同様に力強く荒れていた。日も沈みかけた森の中を、四十はとうに過ぎ五十も少しは出ているかもしれない極端なほど小柄な農家の主婦に手を引かれ、ぼくは前のめりに歩いているのだった。
ぼくたちは黙って歩いた。ブナやらミズナラの間を縫って、下生えの笹をかき分けながら、時には落ちた小枝を踏んづけてポキリと音を立てたりもした。それはすこし湿った音だった。木や草の発する青い匂いが次第に濃くなっていった。時折り遠くで何かの鳴き声がした。鳥のようでもあり小さな獣かもしれなかった。
彼女はほんとうに急いでいるふうであった。それでも真直ぐに登ってゆくことはせず、かなり複雑なジグザグの線をじょうずに歩いてゆくのであった。おそらくは毎日のように通るのであろう彼女にしか分からない細い道があるのかもしれなかった。苔むした倒木を迂回するかと思えばまた、同じような倒木を大胆に踏み越えることもあって、それは常に正しい判断と思われた。彼女は栗鼠(りす)のごとき用心深さと、危険を察知する智恵を持ち、にもかかわらず、危ない場所を正面突破する大胆さも合せ持っているらしかった。黒く煌めく小さな眼で素早く正確に対象物を見て取ることもできるののだろう、彼女は懐中電灯を点灯せず、まるで使い慣れた得物のごとく誇らし気に右手でかざし、歩いてゆくのであった。
較べてぼくは、小枝に足を取られてつんのめったり、倒木の突き出た瘤にいやというほど向う脛をぶっつけて呻いたりした。そしてなにより、ぼくは沈黙に堪えられなかった。
「懐中電灯を点灯したらどうでしょうか」ぼくは、なんという考えもなしに提案してみた。
「ばか。暗くなる」彼女は即答した。
なるほど。懐中電灯を点灯すれば確かにそこだけは明るくなるけれども周辺の薄闇が本当の闇になってしまうという意味であるらしかった。なるほど。ぼくは自分の考えの足りなさを詫び、詫びついでに、こんなことをもごもご言ってみた。最初あなたを見たときは薄暗かったのとだいぶ離れていたせいで歳若な女の子と見間違えてしまいそれゆえにいくらか失礼なもの言いなどしたかもしれませんがどうか許していただきたい。
彼女はケッケと笑った。怒っている気配はなかったのでぼくは言った。こうして旅をしているとよく訊かれるのです。ぼくのような体格のしっかりした健康そうな若者がぶらりぶらぶら物見遊山でもあるまい、きっと何か大きな目的のある旅なのだろう、とね。いつも返答に窮してしまうのですがあなたになら何とかぼくの気持ちをわかってもらえそうな気がします。ぼく大学を出たあと一年と少しばかり会社勤めをしてみたんですけれどどうもぼくには勤め人は向かないようで――
人恋しい夕暮れ時、小柄ながらも自分の母親と同じくらいかそれよりすこし年上らしい女性に力強く手を引かれて歩むうち、すこし甘えが出たのかもしれない。ぼくは喋りに喋ったのであった。ぼくの神経はぼくの肉体ほどには頑丈ではないのです。迷いも悩みも人一倍いや人三倍くらいはあるのです。それで、ぼくとうとう勤めを辞めてしまってこうして旅に出てもうそろそろ三月(みつき)になろうというところでようやく決心がつきやっぱりどうでも小説ってものを書こうと思うのです。
彼女はやはりケッケと笑った。ぼくは慌ててつけ足した。こう見えて学生のころには詩のような小説のようなものを書いてみたこともあるのです。それに小説を書こうと決心したのならばさっさと家へ帰って書けばよいではないかと思われるでしょうがぼくとしてはもうすこしのあいだ旅を続けるつもりです。ぼくの家は裕福とはいえないもののそれなりにゆとりがあって父も母も末っ子のぼくには寛容なものだからいくらか甘えがあるのは認めざるを得ませんがぼくはぼくなりに考えもあって努力もしているので幸福ですしぼくが幸福であるならぼくの父と母もたぶん幸福に思っているでしょうからぼくがこうしてまともな職にもつかずに放浪しているからといって親不孝ってわけではないのです。それにしてもきょうのぼくはなんて運がいいんだろう。あなたに会えたおかげで鄙びた温泉に泊まることができるんですからね。
彼女はもう笑うことはせず、かわりにふと立ち止まった。ぼくも立ち止まり、それでも喋り続けた。ほんとうにありがたいことです。こんな山深い、あ、いやじっさいはそれほどでもないんでしょうけれど、静かな風情のある土地でひっそりとした宿に巡り会うなんて、なんともいえずロマンティックです。これで短編小説の一編でも、あるいはちょっとした詩のようなものを二つか三つでも書ければなんて虫のいいことを考えて嬉しくなったとしても――
再び彼女は強くぼくの手を引っ張って歩き出し、すぐにまた立ち止まった。ぼくは彼女に蹴つまずきそうになって、かろうじて踏み止まった、なぜなら彼女が唐突にしゃがみ込んだからなのだった。おまけに鋭い小声で何か言った。―――でないよっ、と聴こえた。
なんですって? と同じ鋭さでぼくは聞き返した。夢中のお喋りに水を注されていささかムッとしたからか、いや、自分のお喋りを突然に恥じたせいかもしれなかった。
きょうは、ひとりで、ないよ、と彼女は一言一言を区切るように、目前の薄闇を見据えて言うのであった。
もちろんそうですとも、あなたとぼくのふたりです、とぼくは重々しく言った。非常に間抜けな言い種(ぐさ)ではあったけれど、その場の雰囲気からして真剣に言わざるを得なかったのだ。
彼女はしゃがんだままぼくの顔を振仰ぎ、少し気味悪気な目つきで睨んでから、また目前の薄闇に向って呟いた。
「しょうがねえね、ふだんはアタシのほかに見られたりするのを厭がるくせに。きょうはよっぽどの事情があるんだね?」
ここへきてようやくぼくにも事態が呑み込めてきた。彼女の会話の相手はぼくでない。目前の薄闇の辺りに何かがいるのだ。彼女の視線の低さから推量するとおそらく身長二十センチメートルかそこらの小さい生物にちがいない。ぼくは眼を凝らした、が、下生えの笹っ葉や枯れて落ちた枝のほか、そこいらには何も発見できなかった。なにかいるんですか、そこに? とぼくは恐る恐る訊ねた。
彼女は呆れ顔で、あんたの眼は節穴かえ、と言いざまぼくの腕をグイと引いてしゃがませた。そして、ぼくの耳元でこう囁くのであった。そこに、ほら、こまいものが三人と一匹おるであろ?
三人というからには、こまい、つまりは小さい人が三人いるのだろう。一匹というのがなんだかわからないけれども。ぼくはさらに眼を凝らした。やっぱり何も見えやしなかったが、はあ、はあ、なるほど三人と一匹ね、などといいかげんな相槌を打った。何やらくやしかったのである。
「人間嫌いなんだか、よほど恥ずかしがり屋なんだかで、アタシよりほかのひとには見られるのをよほどはばかっている連中なんだがね、めずらしいこった。それともあんた」と彼女はアッハッハと笑いを挟んで言ったのだった。「人間だと思ってもらえなかったのかもしれないねえ」
ぼくの自尊心はもちろん多少傷つき、しかしながらそう言って笑っているあなただって人間だと思われてないわけじゃないか、などと憎まれ口を聞きたくもあったが、初対面で道案内をしてもらっている身でもあり、そもそも何やら異様なことに巻き込まれている気がして、ぼくは何も言えなかった。
彼女はちんまりとしゃがんだまま、真顔になり、ふむふむだのふーむだのと唸っていた。どうやらこまいものらの陳情を聞いている賢婦の趣きなのであったが、ぼくには彼女の唸り声のほかはなにも聞こえないのであった。やはりちょっとくやしくて、百姓の女は忙しいんで急がねばよ、じゃなかったんですか? などと茶々を入れてみたくもあった。それに、こんな異様なことに薄くなじみつつある自分自身が空恐ろしくも思われた。が、もっとも顕著な気持ちは、淋しさなのであった。ぼくひとりが蚊帳の外、そういう淋しさなのであった。大きなリュックを背負ったまま無理にしゃがんでいる自分の姿もいかにも淋しげで間抜けだろうと想像された。
「まあいいさ」と彼女が言った。「このおひとのことは木かその節穴だと思っておればいいよ。明日にはこの土地を出てゆきなさる旅のおひとだから。おまえたちを見たことは他言せぬよう、アタシからもよくよく口止めしておくからに」
木かその節穴か――いよいよ淋しくなり、ぼくは、ほぅと溜め息を吐いた。彼女はぼくの気分を察知したのか、ぼくのシャツの腕をなれなれしくひっかいて言った。
「その、耳がみどり色したやつはオキというのだ。そっちの赤い鼻をしたギョロギョロ眼(まなこ)はツツグチ」
どうやらこまいものらを紹介しているつもりらしかった。
「ふたりのあいだでおろおろうろうろしてるネズミ色の肌をしたのはナルメ。こんぐらいのもめ事を片つけることもできんで、ちっ、役に立たんやつだねナルメは」
「どんなもめ事なんですか?」思わずぼくは訊ねた。
彼女は眼を剥いた。「あんた、目は節穴で、耳は貝殻か。オキとツツグチは、ポチの所有をめぐって争っているのだ」
「ポチ? 犬みたいな名前だな」ぼくはうかつにもそう言ってしまった。
彼女はさらに眼を剥いた。「犬だよ。こまいこまい犬だよポチは。ポチといえば犬と、昔から決まっておろうが。ナルメが連れているのがそのポチだよ。よしよし吠えるなポチ、急(せ)くでないよ、吠えるでない。すぐにアタシがおまえの処遇を決めてやるから安心おし。こら、ナルメ、ポチを押えておけ。まったく気の利かぬやつだナルメは。まあ、その間抜けぶりがおまえの可愛げでもあるけどな。さあ、さて。よっく考えねばよ」彼女は腰を落ち着けた。賢し気な眼は、ぼくを見るときとはまるでちがう親しい者たちを見るときの優しさに満ちていた。彼女はぼくの懐中電灯を――もちろん点灯せずに――象徴的な杖かなにかのように効果的に使い、語りはじめた。
「オキよ。おまえはときたまアタシの家にも現れて草むしりの手伝いだの風で飛んでった洗濯物を拾ってきてくれたりだの、まこと心優しいまめな性質であるよ。反対に、ツツグチ、おまえは、やくたいもないばかでかい音をさせて人を驚かし、あとであれはオレがやったのだなどと自慢して歩いたりする。音だけならまだよいが、おまえは道行く人の首筋をこっそり舐(ねぶ)ってゾッとさせたりもする。実にたちの悪いいたずら者であるよ。だがしかし、だからといってアタシの捌(さば)きは、おまえたちの性質に左右されたりはしない。公平でなければならん。さあ、さて。争点であるポチは、ベイベイの実をみつけるのがすこぶるじょうずであるな。ベイベイの実は、ポチはもちろんのことおまえらみんなの好物だな。これまでポチはベイベイの実を見つけると、半分を自分で食い、残りの半分をたまたま近くにいた者に分け与えていたのだな? うむ、そうか、それが習性であるとはいえ見上げた行いではないか。それを、まあ、なんということだ、赤っ鼻ツツグチのやつが腕力と声の大きさにものをいわせてひとりじめしようと、つまり、ポチの飼い主になろうと言い出した。それに対し、オキは当然、異をとなえた。なぜなら、乱暴でわがまま勝手なツツグチに飼われる身の上とならば、ポチの自由は疎外され幸福でなくなり、ベイベイの実もほかのみなの口には入らなくなる。そんならオレが受けて立とうと、オキもポチの飼い主に立候補したというわけだな。オキの言い分では、オレがポチの飼い主になれば今までどおりポチを自由にしておくし、ベイベイの実も今までどおり半分はポチに、残りの半分は公平にみなに分けて暮らしてゆこうというのだな。いかにもみどり色の耳のオキらしい優しさと勇気に満ちた申し出であるよ。右相違ないか、ナルメ? 相違ないな、ナルメ。ついでに言っておくが、ナルメよ、おまえはいつに変わらぬ腰抜けぶりで、オロオロするが関の山とは情けない、が、しかしである、このもめ事をアタシに捌いてもらおうと思いついたは褒めてやらねばなるまい。おまえの眼ん玉はちっこいちっこい赤い眼ん玉ではあるが、なかなかに人を見るのは確かな眼ん玉ではあるよ。さあ、さて。せっかくだから、参考までにあんたの意見も聞いておこうか」
彼女はだしぬけにぼくの顔を見てそう言ったので、ぼくは仰天して尻餅をついてしまった。
「びっくりするこたぁないだろ。旅の恥はなんとやらいうではないか。どんなに馬鹿げた意見でも、この際ひとつ、ぶってみてはどうだね」
ぼくは、目前の薄闇には何も見えず、そこいらからいかなる音声も聴こえてこないのだと言うべきだったのかもしれない。けれど、やはり奇妙な見栄にとらわれていたのだった。
「ぼくが思いますには――」
「ふむ」
「あ、その前にひとつお尋ねします」
「はいよ」
「そもそもポチは、誰のものだったのでしょうか」
「ポチは誰のものでもないよ」
「では、野良犬ポチをぜひオキさんの飼い犬に」馬鹿馬鹿しいほどの熱意をもってぼくは言った。「そうすれば、オキさんは優しくあたたかくポチを護り、幸福なポチはみなに尽くすことでしょう。ベイベイの実もポチとみなさんのものになるでしょう」
ぼくは目前の薄闇に眼を凝らし、耳を澄ませてみたけれど、もちろん、ソヨともザワとも音はせず、何も見えはしなかった。
彼女は重々しく言った。
「なるほど、それもよかろう。が、アタシの考えは違う。ポチは誰のものでもない。ポチの主人はポチだけだ」
「なんですって」ぼくはちょっとムキになってしまった。「それじゃあ何の解決にもならないじゃありませんか。何も変わらないし何も前進しない!」
「まあまあ、お若い人はすぐにカッカするからいけないね。何も変わらない何も前へ進まないほうがいい場合だってあるのさ。それに、ツツグチの立場というものも考えてやらねばいけないよ。たしかにツツグチは厄介なやつではあるが、こまいものらの仲間にはちがいない。ツツグチの心持ちも案じてやらねばなるまいよ」
ぼくはうつむいた。自分の配慮の無さが哀しかった。
「まあ、そうしょげるでないよ」
彼女は温かな小さい手でぼくの背中を撫でさすってくれた。
「さあ、さて。これで捌きはついたはずだが、よいかナルメ? よいな。オキも納得か? 納得だな。ツツグチ、文句はあるか? ないな。ポチも喜んでおるようだ。よし」
彼女は勢いよく立ち上がった。ぼくも慌てて立ち上がろうとして、痺れた脹ら脛に裏切られ、横座りにへたってしまった。
「そうだ、忘れるところであった。今見たことも聞いたことも、誰にも言うでないよ。きっと馬鹿にされたり笑われたり、ひょっとすると気味悪がられて、いやな思いをするだけだから。ちっこい温泉の親切な夫婦にも、喋ってはいかんよ」
再びぼくの手を引いて歩き出し、彼女は言うのであった。「百姓の女は忙しい。んで、急がねばよ」
そして、めざましい勢いで歩いてゆくのであった。
木々の間を明りが動いてゆくのが見えた。自動車のヘッドライトであった。今度は大きく見えた。森の出口はもうすぐだった。
森を抜けてアスファルトの道に出ると彼女は懐中電灯をぼくの手に押しつけた。
「アタシの家はこっち。あんたが行くちっこい温泉はあっち。この道なりに歩いていくと左側にあるよ。じきに着く。もう迷うことはあるまいよ」
少し寒そうに肩をすぼめて立っている彼女は、どこからどう見てもふつうの農家の主婦であった。ぼくは狐につままれた気分で歩きだした。十歩も歩いたあたりで、道案内の礼を言うのを忘れていたことに気づき、振り返った。
暮れなずむアスファルトに佇んで、彼女が思いっきり舌を出しているのが見えた。
(了)